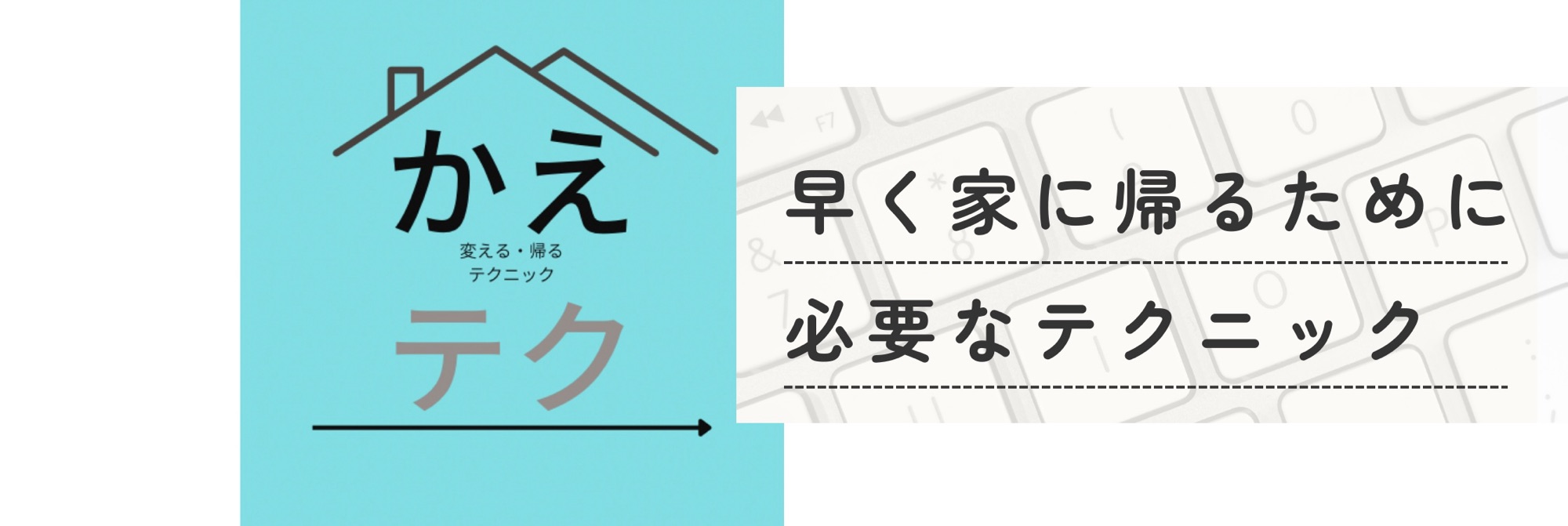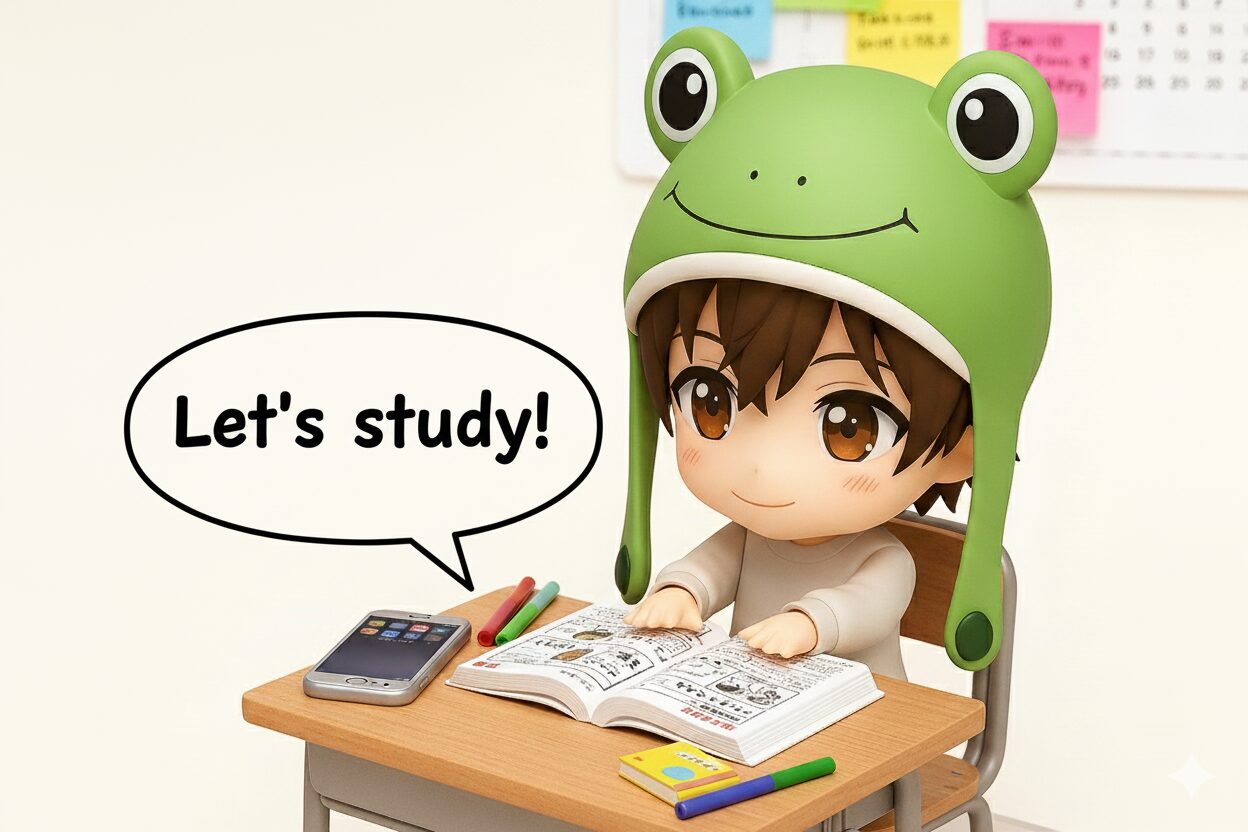どうも、定時デカエルです!
このブログ「かえテク!」では、あなたの仕事を「変える」ための、そして、早く「帰る」ためのテクニックや考え方を発信しています。
突然ですが、あなたは勉強が好きですか?
学生時代の教科書、社会人になってからの専門書や資格の参考書…。「うわっ、分厚い…」「文字ばっかりで眠くなる…」なんて、一人で読み進めるのに苦労した経験、ありませんか?
わからない言葉が出てきても、質問できる相手がすぐそばにいるとは限りません。結局、途中で挫折してしまった…なんてことも。
もし、あなたの隣に24時間365日いつでも、どんな質問にも答えてくれる超優秀な家庭教師がいたら、どうでしょう?
実は、そんな夢のような話が「生成AI」を使えば実現できてしまうんです。今回は、AIをあなただけの専属家庭教師にして、難しい本もスラスラ頭に入ってくる、新しい勉強法をご紹介します。この方法なら、勉強時間を圧倒的に効率化できて、仕事やプライベートの時間をもっと豊かにできますよ!
勉強の「わからない」が「わかる!」に変わる時代が来た
今までの勉強は、基本的には「孤独な時間」でした。教科書や参考書を読んで、わからない部分があっても、自分で調べるか、誰かに聞けるタイミングを待つしかありませんでした。
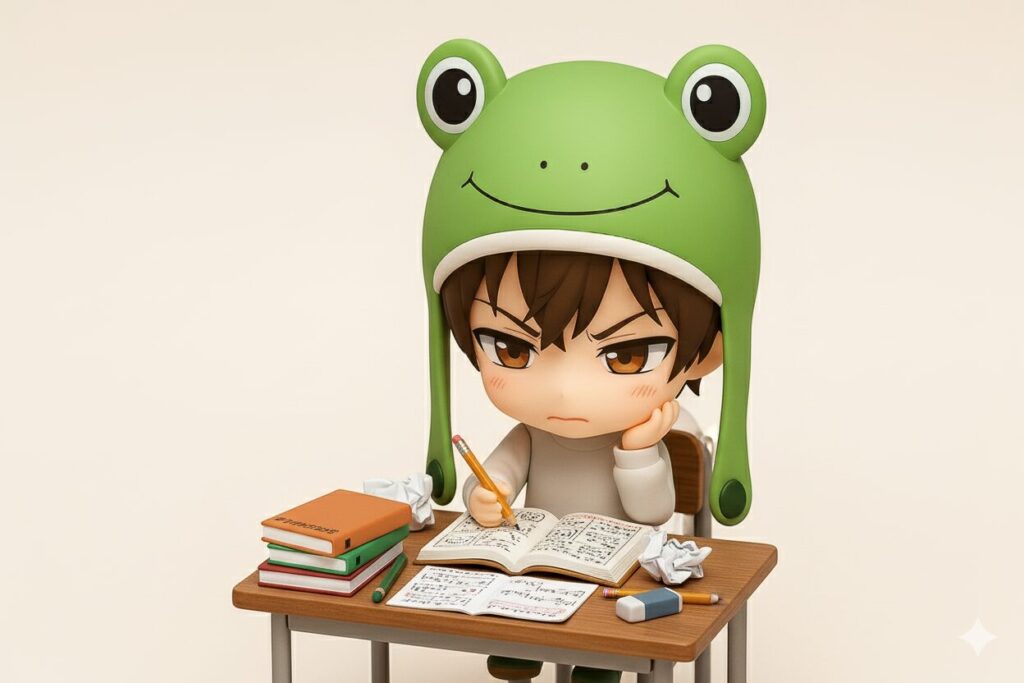
しかし、生成AIの登場でその常識は覆されました。ChatGPTやGemini、Perplexityといった生成AIは、まるで人間と会話するように、こちらの質問に答えてくれます。
つまり、本を読みながら、わからないことが出てきた瞬間に、隣にいる先生に「これってどういう意味?」と聞けるわけです。これって、革命的だと思いませんか?
【初心者向け】生成AIで勉強を効率化する「AI家庭教師」の始め方
「なんだか難しそう…」と思った方もご安心ください。始め方はとってもカンタンです。
ステップ1:まずはAIに「先生役」をお願いしよう
まずは、あなたが使いたい生成AIを開いてください。
PCではなくスマホの音声モードが手軽でおすすめです。勉強ですので気軽に始められることが大切です。
最初にAIに「役割」をお願いしてみましょう。
これをすることで、AIの回答がよりあなたの目的に沿ったものになります。
【お願いする時のプロンプト例】
「今から『〇〇(本の名前)』という本を読みます。私はこの分野の初心者なので、わからないことがあったら質問します。その際は、専門用語を避けて分かりやすく解説してください。」「〇〇の資格取得のために勉強を始めます。今からする質問には、〇〇の試験対策になるように答えてください。」
ステップ2:本を読みながら、わからないことはスグ質問!
準備はこれだけです!あとは教科書や参考書を読み進めて、少しでも「ん?」と思った単語や説明があれば、都度AIに質問していくだけ。
- 「〇〇ってどういう意味?」
- 「○○の説明で〇〇って書いてあるけど、どういうこと?」
こんな風に、友達に話しかけるような感覚で大丈夫です。

ステップ3:深掘り質問で「なるほど!」を引き出すテクニック
一度の回答で理解できなかった場合も、遠慮はいりません。AIは何度でも、嫌な顔一つせず付き合ってくれます。
- 「ごめん、まだ難しいから、もっと簡単に説明して」
- 「具体的な例を挙げて説明してほしいな」
このように追加で質問することで、あなたの理解度に合わせた解説をしてくれます。まさにマンツーマン指導です!
学習効果が劇的に変わる!AI勉強法のおすすめ応用テクニック3選
この勉強法の真骨頂は、教科書だけの学習では絶対にできなかった「対話による深い理解」にあります。特におすすめの応用テクニックを3つご紹介します。
応用テク1:「高校生活に例えて!」自分だけの例え話で記憶に定着
これが私が一番強調したいポイントです。例えば、選挙の仕組みについて勉強している時、ただ説明を読んでもピンとこないことがありますよね。そんな時、こう聞いてみるんです。
「選挙の比例代表制について、高校の生徒会選挙に例えて説明して!」
するとAIは、「『文化祭の出し物を決めるA党』や『体育祭を盛り上げるB党』といった各グループに投票して、その得票数に応じてクラス委員の人数が決まるようなものですよ」というように、あなたにとって身近な世界に置き換えて解説してくれます。これにより、難しい概念がスッと頭に入り、記憶にも残りやすくなります。
社会人の方なら働いている会社や業界に例えてもらうこともおすすめです。
応用テク2:「この理解で合ってる?」自分の言葉で確認して知識を確実なものに
勉強に慣れてきたら、受け身で質問するだけでなく、自分から能動的に働きかけてみましょう。
「〇〇という説明があったけど、これってつまり、△△っていう理解で合ってる?」
このように自分の言葉で要約して質問することで、AIがその理解が正しいか、どこが違うかを的確にフィードバックしてくれます。この一手間が、知識の定着を飛躍的に高めてくれます。
応用テク3:やり取りを「まとめて」もらえば、最強の復習ノートが完成!
勉強が一段落したら、最後にこうお願いしてみましょう。
「今までのやり取りを基に、今日の学習内容を箇条書きでまとめて。」
これだけで、その日の学習の要点が詰まったオリジナルノートが完成します。自分でノートをまとめる手間が省け、予習・復習が驚くほど楽になりますよ。
どのAIがいいの?おすすめAIと選び方のポイント
「どのAIを使えばいいの?」と思うかもしれませんが、結論から言うと、まずは色々試してみて、自分に合うAIを見つけるのが一番です。ChatGPT、Gemini、Claudeなど、それぞれに個性があります。
会話モードの話し方や回答内容で自分に合うAIを使っていくのが良いと思います。
個人的な最近のおすすめは「Perplexity(パープレキシティ)」です。このAIは検索エンジンをベースにしているので、事実に基づいた回答が得意で、情報ソースも示してくれます。いわゆる「ハルシネーション(AIがもっともらしい嘘をつくこと)」が少ない印象で、無料版でも日本語の会話が非常にスムーズなので、勉強のパートナーとしてかなり優秀だと感じています。
時に「いい質問ですね!」なんて褒めてくれることもあって、なんだかモチベーションが上がったりもします(笑)。ぜひ、あなたにとって最高の「AI先生」を見つけてみてください。
まとめ:AIと一緒に、学ぶ楽しさを再発見しよう!
今回は、生成AIをあなた専属の家庭教師にする新しい勉強法をご紹介しました。
- 最初にAIに「先生役」をお願いする
- わからないことは、その都度すぐに質問する
- 「身近な例え」や「要約」で、より深く理解する
- 最後に「まとめて」もらって、復習に役立てる
この方法を使えば、これまで一人で抱え込んでいた「わからない」というストレスから解放され、学ぶこと本来の楽しさを再発見できるはずです。
勉強が効率化されれば、その分、早く仕事を終えられたり、プライベートな時間が増えたりと、あなたの生活はもっと豊かになります。ぜひ今日から、あなたの勉強を「変えて」みませんか?
あわせて読みたい
今回は「勉強」におけるAI活用法をご紹介しましたが、生成AIはあなたの生活をさらに豊かにする可能性を秘めています。仕事や日常のタスクを効率化するヒントに、こちらの記事もぜひご覧ください。