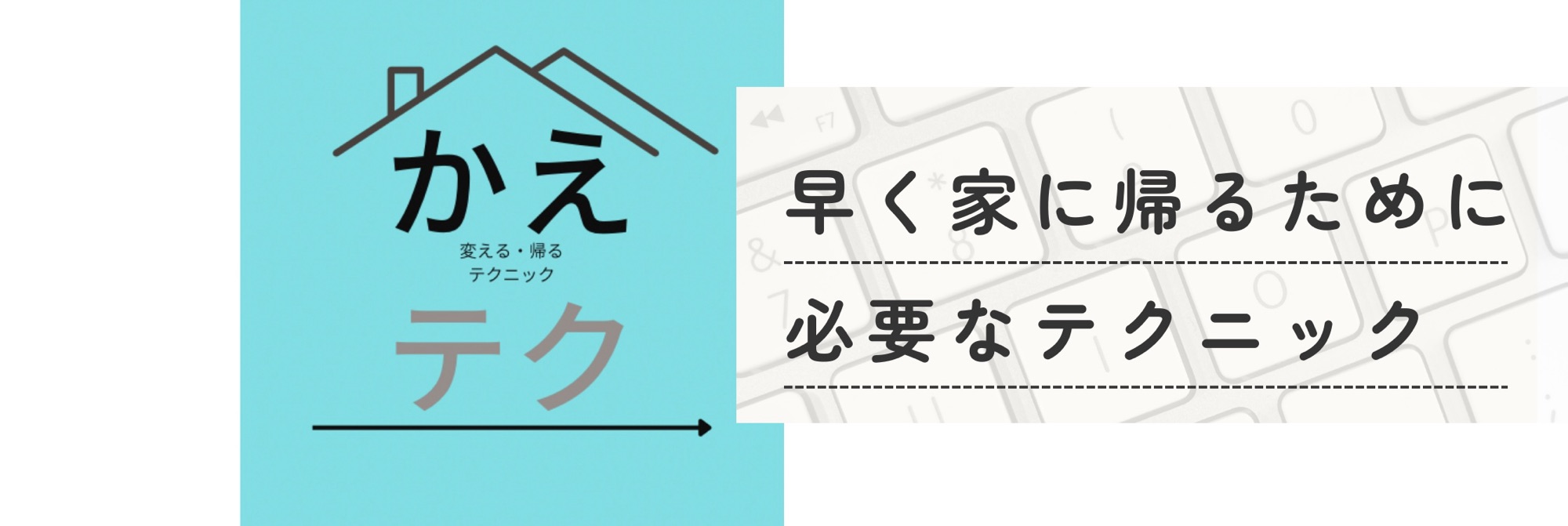こんにちは、定時デカエルです!
仕事を「変える」、早く「帰る」ためのテクニックを発信しているこのブログ「かえテク!」。今回は、私たちの仕事を劇的に変える力を持つ「生成AI」、それをもっと効果的に使う意識がテーマです。(代表例としてChatGPTを挙げていますが、GoogleのGeminiなど他のAIでも全く同じように使えるテクニックです!)
「ChatGPTを使ってみたけど、期待した答えが返ってこない…」
こんな風に感じたことはありませんか?その原因、もしかしたら私たちが長年慣れ親しんだ「Google検索」のような感覚で、AIに指示を出してしまっているからかもしれません。
この記事では、AIとの対話を劇的に変える「発散」と「集中」という2つの思考法と、従来の検索との違いを解説します。このコツさえ掴めば、AIをあなたの「最強の相棒」に変身させ、仕事をサクッと進めて定時で帰るための強力な武器になりますよ!

なぜAIはうまく使えない?原因は「検索キーワード」を投げるだけの使い方をしているからかも
私たちは普段、Googleなどで検索するとき、「〇〇 やり方」「〇〇 意味」のように、短いキーワードで一つの正解を探そうとしますよね。
そして多くの人が、無意識に生成AIに対してもこの「検索」と同じように、いきなり完璧な答えを求めてしまいます。しかし、AIの真骨頂はそれだけではありません。答えのない問いに対して、アイデアを無限に広げる「発散」も大得意なのです。
この違いを知らないままでは、AIの能力の半分も引き出せていません。例えるなら、こんなイメージです。
- インターネット検索:膨大な蔵書から、あなたの求める本をピンポイントで見つけてくれる「超優秀な司書」。
- 生成AI:あなたの曖昧な相談にも乗り、一緒にアイデアを考え、壁打ちにもなってくれる「賢くてクリエイティブな同僚」。
「同僚」であるAIの能力を最大限に引き出すために、まずは「発散」と「集中」の役割をしっかり理解しましょう!
実はあなたもやっている?「発散」と「集中」の正体
「発散」や「集中」というと、少し難しく聞こえるかもしれません。でも実は、これらは私たちが普段の仕事や生活で、ごく自然におこなっている思考のプロセスなんです。
例えば、こんな経験はありませんか?
- 会議でのブレスト(発散)と絞り込み(集中)
「まずは質より量!とにかくアイデアを何でも出そう!」と自由に意見を出し合うのが「発散」。そして、「出たアイデアの中から、『予算内か』『実現可能か』といった基準で評価し、有力な候補を3つに絞り込もう」と、選択肢を整理していくのが「集中」です。 - ランチのお店選び(発散)と絞り込み(集中)
「パスタもいいし、中華も捨てがたいな…あ、駅前に新しい定食屋ができたらしいよ?」と選択肢を広げているときが「発散」。そして、「昨日はイタリアンだったからパスタはやめておこう。中華は午後の会議を考えると匂いが気になるかな。そうなると、あの定食屋が一番良さそうだ」と、条件を加えて選択肢を絞り込んでいくのが「集中」です。
このように、私たちは無意識に思考を広げたり(発散)、絞り込んだり(集中)しています。生成AIをうまく使う最大のコツは、この自然な思考のプロセスを、AIとの対話の中で「意識的に」やってあげることなのです。
【使い分けマップ】あなたの目的はどれ?「発散」「集中」「組み合わせ」の最適な使い方
あなたの「今やりたいこと」に合わせて、AIへの指示を使い分けるのが最大のコツです。ここでは3つの場面に分けて、具体的な使い方を紹介します。
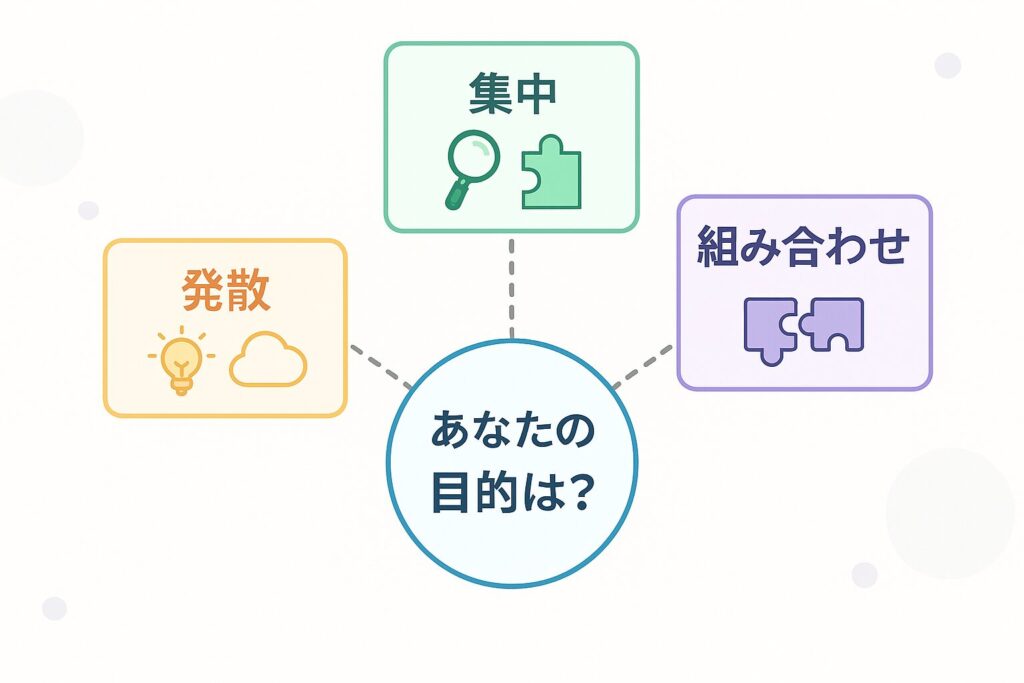
1. 「発散」が活きる場面:アイデアの壁打ちや選択肢が欲しいとき
自分一人では考えが凝り固まってしまう…そんな時はAIに「発散」の指示を投げて、思考の幅を広げてもらいましょう。質より量を求めるのがポイントです。
- こんな時に便利!
企画の切り口探し、キャッチコピーの大量生産、新しい視点の発見
【発散のプロンプト例】
「あなたは経験豊富なマーケティングプランナーです。健康志向の30代社会人向けに、平日のランチタイムに開催するオンラインセミナーのテーマ案を、これまでにない斬新な切り口で10個、箇条書きで提案してください。」
2. 「集中」が活きる場面:ゴールが明確な単純作業を任せたいとき
これは従来のインターネット検索の感覚に近い使い方です。「〇〇して」というゴールが明確な作業は、AIに任せれば一瞬で片付き、大幅な時短につながります。
- こんな時に便利!
文章の要約、翻訳、メールの文章校正、複雑なExcel関数の作成、さらにはインターネット料金プランの比較やPCスペックの比較といった面倒な情報収集もAIに任せることができます。
【集中のプロンプト例】
「あなたは優秀なアシスタントです。以下の会議議事録を、300字程度で要約してください。【決定事項】と【今後のタスク】が明確にわかるように、見出しをつけてまとめてください。[ここに議事録を貼り付け]」
3. 「組み合わせ」が活きる場面:ゼロから何かを創り上げたいとき
これがAI活用の真骨頂です。まず「発散」で可能性を広げ、次に「集中」で形にしていく。このキャッチボールを繰り返すことで、一人で考えるよりも速く、質の高い成果物を創り上げることができます。
- こんな時に便利!
企画書の作成、イベントの計画、プレゼン資料の構成案、記事執筆
【組み合わせのプロンプト例】
- Step1:発散
「あなたは社内イベントの企画担当者です。社内のコミュニケーションを活性化させるためのイベント企画案を、部署や役職の垣根を越えて交流できるという観点で5つ提案してください。」 - Step2:集中
「ありがとうございます。その中で提案された『部署対抗eスポーツ大会』について、開催に必要なタスクを箇条書きでリストアップし、簡単なスケジュール案も作成してください。」 - Step3:深掘り(集中)
「助かります。Step2で出たタスクの中から『参加者募集の告知』について、社内SNSに投稿するための告知文のドラフトを作成してください。楽しそうな雰囲気で、初心者でも参加したくなるような文章をお願いします。」
まとめ:AIとの「対話」で、最強の仕事パートナーを育てよう
今回は、生成AIから期待通りの答えを引き出すための「発散」と「集中」の使い分けについて解説しました。
重要なポイントは、AIを「答えを一つだけ出す検索エンジン」だと思わないこと。
答えが明確な単純作業は「集中」でサクッと片付けてもらい、答えのない創造的な仕事は「発散」と「集中」の対話を繰り返す。この使い分けができるようになれば、AIはあなたの意図を的確に理解してくれる「最強の相棒」に進化します。
ただし、AIは時々、事実と異なるもっともらしい情報を生成することがあります(ハルシネーション)。特に重要な情報やデータについては、最終的に自分で事実確認を忘れないようにしましょう。
AIとの無駄なやり取りで悩んでいた時間が、これからは創造的な仕事を生み出す価値ある時間に変わります。結果、仕事が早く終わり、自分の時間も増える。まさに「かえテク!」ですね!
ぜひ、明日からの仕事で「これは発散?集中?」と考えながら、AIとの対話を楽しんでみてください!